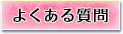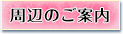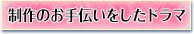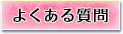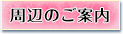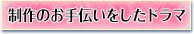|
◆◆国際山岳ガイド・降籏義道がご案内◆
|

左から白馬岳、真中が小蓮華岳、右端が乗鞍岳から天狗原。この付近に雪形が集中している
春になるといろいろな雪形が現れる。残雪が白い形で造る雪形と雪が消え黒い部分で造る雪形の二通りがある。白馬岳の由来となった馬の雪形は有名だ。でも、何処にあるかは余り知られていない。春の楽しみを見つけてください。
|
 |
白馬岳の馬。
春この馬形ができたら田植えの準備を始めたという。馬を使って行う代掻きという作業からこの馬を『代掻き馬』と呼び、それが『代馬』から『白馬』と名前がなまったという。だから「ハクバ」ではなく「シロウマ」が正しいという説がある。でも「白馬岳」という文字は江戸末期、松本藩の古文書に突如として現れる。山廻り役人が書き残したものだ。地元では両替岳とか駒ヶ岳とかいくつかの呼び名があった。「ハクバ」の名前がででくるのは明治16年、白馬岳の初登頂とされる郡長(当時の地方事務所長)と小学校長の白馬登山日記である。「シロウマ」がでてくるのはその後10数年たってからだ。さて、「ハクバ」か「シロウマ」でしょうか? |
| |
|
 |
これが「代掻き馬」? です。ハクバの由来となる雪形です。左に頭部があり、尻尾は右端で稜線まで跳ねあがって見えます。場所は白馬岳の右端、一番低いところの鞍部に尻尾が上がってきています。頭部は白馬岳の山頂方面を見ています。
|
|
 |
これが子馬。小蓮華岳右端に出る
白馬岳の馬に対して、これを子馬と呼ぶ。白馬岳のそれより「馬」らしいかも・・・。 |
|
|
 |
これが子馬のアップ。小蓮華岳の右端のピーク近くに現れる。 |
 |
|
これは種まき爺さん(右)
子馬の前足の延長線上に出ている。
左の雪形は腰をかがめて田植えをしているように見える。
この二つの雪形は田植えをする早乙女達にも見える
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
小蓮華岳の中央部に現れる、これも種まき爺さん。
下のアップと照らし合わせて探して下さい。 |
|
|
|
 |
種蒔き爺さん。
少し前かがみに見えます。背中の部分が雪が消えすぎ、黒くなりすぎていますから分かりにくいかもしれません。小蓮華岳の中央部に現れます。 |
 |
通称ニワトリ
ニワトリが白く浮き上がって見える。乗鞍岳の斜面中央部に大きく現れる。比較的見つけやすい雪形だ。
ワトリに見えるでしょうか。
カモシカという人もいます。山域的にはカモシカのほうが合っているかも・・・ |
| |
|
|
|
 |
|
白馬美人!?
5月末から6月始めにかけて乗鞍岳の山頂に現れる。
消えかかったニワトリのクチバシに口を近づけるように、黒髪をなびかせて・・・・。
実はこれほとんど白馬村でも知られていないみたい。
中学の頃、仲間内で評判になったのだが・・・。 |
| |
|
|
 |
|
どんな美人も近くで見ると・・・・
雪の付き方によってか顔型がシーズンごと違う。
色白のすごい美人に見えるときもある。
|
 |
|
五竜岳の武田菱。
戦国の武将、武田信玄。武田家の家紋が「四つ菱」である。五竜岳の頂上直下に現れる。武田家の家紋の御菱(ごりょう)が出ることから、《ごりょう》から《ごりゅう》に訛って、《五竜》になったという説もあるが、定かでない。 |
| これが武田菱だ |
|
|
|
 |
|
ライブカメラからの白馬山麓と北アルプス | 毎日更新!!今日の白馬岩岳スキー場(冬季のみ)
白馬のピンポイント天気予報 | 今の天気図 | 岩岳ゆりの園からのライブカメラ
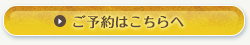
i-モードでも展開中!