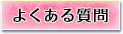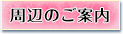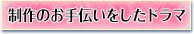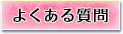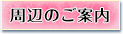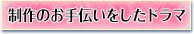|
栂池自然園、展望湿原から秋の大雪渓を望む。右は白馬岳。
左の黄色はダケカンバ、赤い葉はナナカマド、手前は見事な草紅葉に染まっている。
|
|
|
|
 |
白馬大雪渓から暑中お見舞い申し上げます。流れ出る水は0度に近く、このように
温度差から水蒸気をあげていることが多い。気温は10度前後、まさに冷蔵庫の中である。
|
|
|
|
 |
6月に入るとブナの原生林も新芽を吹き出した。バック白馬岳
|
|
|
|
|

カタクリの花。木にコブシの花をつける頃、その下にカタクリが可憐に咲き誇っています。
カタクリは白馬の村花でもあります。群生地はあちこちにあります。
|
|
|
 |
コブシの花と五竜岳。下の写真の福寿草が咲き、そしてコブシ、それから桜と白馬の
春がやってくる。桜が満開となるのが5月連休中である。 |
| |
|
|

|
福寿草。 白馬では一番に咲く花である。
一株のみで咲いていることはむしろ少ない。必ず1㎡以内に他の数株がある。
いわゆる小さいながらも群落をつくっている。
大きいものは何万株の群落にもなり、あたかも黄色いジュウタンを敷いたように見える。
白馬にはあっちこっちに群落がある。 |
| |
|
| |
|
| |
|

|
スキーシーズンが始りました。岩岳山頂ゲレンデから見る白馬三山。
右から白馬岳、杓子岳、白馬鑓ヶ岳。 |
| |
| |
| |
|

|
神々の山嶺は私の友人、夢枕獏氏の著書のタイトル。今の北アルプスは、
まさに神々の住む世界です。最も山が荘厳に見えるときです。 |
| |
| |
| |
|

|
峰々の白、真中の紅葉、手前の緑。これが三段紅葉です。
10月初旬に冠雪がある。三段紅葉となります。白馬では10月末まで楽しめます。
山麓の木々がその葉を落とす11月中旬には、麓も初雪がきます。 |
| |
| |
| |
| |
|

|
大雪渓の紅葉は余り知られていません。
三号雪渓の残雪と岩肌、芝紅葉を絡めた紅葉は味があります。
でも、見に行くにはちょっと大変です。 |
| |
| |
| |
| |
| |
|

|
八方尾根からの五竜岳と鹿島槍ケ岳。いずれも日本百名山。栂池自然園などの
ナナカマドやダケカンバが染まり始めるのは10月初旬からです。 |
| |
| |
| |
| |
|

|
白馬岳(2932m)です。猿倉から見ています。ここには猿倉荘があり、白馬岳の登山口となっています。
ちなみに写真左の岩が猿倉の名の由来となった岩壁です。
昔、岩壁のことを「倉」とか「菱」(ヒシ)と呼んだのです。八方尾根の黒菱(クロビシ)もその一例です。 |
| |
| |
 |
|
新緑のシーズンがはじまりました。春です。木々が芽吹き、小鳥がさえずり、
花々が咲き出しています。
日本百名山の五竜岳と鹿島槍ケ岳(左奥)です。
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|

|
| 岩岳山頂からの八方尾根スキー場。正面の山は日本百名山、鹿島槍ケ岳。 |
| |
| |
| |
|

|
厳冬期の杓子岳(右)と白馬鑓ヶ岳。その荘厳なまでの美しさは、ヒマラヤや
アルプスを思わせる。 |
| |
| |
| |
| |
|

|
雪が降り下がった朝。山腹の白く薄っすらとした雪化粧は霧氷です。
陽が昇ってくると消えてしまいます。左から鹿島槍ケ岳、五竜岳、右が八方尾根です。
五竜岳の下、杉の木の間に白馬ジャンプ台が見えます。 |
| |
| |
| |
|

|
白馬山麓は紅葉が盛りです。でも白馬三山はすでに真冬。これから低気圧が通過する
度に雪は山麓へ降りてきます。通常、11月10日前後に初雪があり、その1ヶ月後の
12月中旬に白馬山麓も根雪となり、春まで雪が消えません。 10下旬 |
| |
| |
| |
| |
|

|
当館レストランからの白馬鑓ヶ岳(左)と杓子岳。
手前の岩岳スキー場も紅葉の盛りです。手前の緑と合わせて三段紅葉と呼びます。
空の青と稜線の白、そして山腹の赤で三段紅葉だという人もいます。
どちらでも、その鮮やかさに変わりはありません。これが秋の白馬の顔です。 10月中旬 |
| |
| |
| |
| |
| |
|

|
クルマユリ(ユリ科ユリ属)車百合
お盆過ぎから咲き出す高山植物の代表格である。背丈も50cm前後と大きく花の直径も
5cmと目立つ。ここ大雪渓の横でも群生しているが白馬鑓ヶ岳の南斜面、大出原
(オイデッパラ)では、斜面全体が赤く染まるほどの群生地として名高い。9月初旬
|
| |
| |
| |
|

|
八方尾根からの白馬三山。大出(オイデ)原・・・白馬鑓ヶ岳の左下、カールの底・・・に残る雪も
小さくなった。でもこの雪が消える前に初雪がくるでしょう。 8月下旬 |
| |
| |
| |
|

|
白馬三山、右から白馬岳、杓子岳、白馬鑓ヶ岳と続く。左の残雪の多い広い斜面は大出(オイデ)原と呼ぶ高山植物の宝庫である。流れは白馬大雪渓を源流とする松川。この下流1Kmで姫川に合流し日本海へとそそぐ。
河口における水質検査で毎年日本一の折り紙がつけられている。
8月初旬 |
| |
| |
| |
| |
|

|
白馬大雪渓、上部
左のピークは杓子岳。正面の鞍部右側の雪渓が小雪渓。左下から中央に向かって雪渓が赤く染まっていますが、これは道しるべにつけた「紅ガラ」の染料の色です。 7月中旬 |
| |
| |
| |
|
|
|
|

|
|
大出(オイデ)の吊橋。下を流れる川は姫川。源流に白馬大雪渓を持ち、河口における水質検査で
毎年日本一の清流のお墨付きをもらっています。
山は白馬三山。右から白馬岳(2932m)、杓子岳( 2812m)、白馬鑓ヶ岳(2903m)。
右端が小蓮華岳(2769m)。白馬と小蓮華の鞍部に出るのが白馬岳の名前の由来になったという
雪形である。 5月初旬

栂池自然園上からの白馬三山。
天狗原への途中から見た三山。中央の白い谷が白馬大雪渓、杓子岳と白馬鑓は重なっている。
3月

冬の不帰(カエラズ)の嶮。
右から天狗尾根、天狗の大下りから最低鞍部が通称「不帰のキレット」。そして三角形の
ピークが不帰Ⅰ峰、次の台形の山がⅡ峰(右が北峰、左が南峰)、小さなピークが三つある
のがⅢ峰(右からA・B・Cピーク)。次の三角形が唐松岳、左端が八方尾根の頭(カシラ)になる。
1月

白馬大橋からの白馬三山。
右から白馬岳、杓子岳、白馬鑓ヶ岳。山麓に初雪が来た朝の写真です。 11月中旬

新雪の白馬岳と紅葉
白馬岳に初雪がきた。山腹はブナなどの紅葉が盛りです。 10月中旬

八方尾根の黒菱平
池に白馬岳を映している。黄色い花はニッコウキスゲ、白い花はコバイケイソウ。
7月中旬
|

|
|
不帰(カエラズ)の嶮。
白馬三山と唐松岳の間にある不帰の嶮は昔、難所として知られた。ここを登ったら帰って
これないことからこの名がついた。今はハシゴやクサリが整備され危険はない。
でもこの時期(6月)はルート上にキノコ雪が残り不安定この上ない。縦走は7月に入って
からが無難だ。右の最低鞍部が通称、不帰のキレット。続いて不帰のⅠ峰、Ⅱ峰、Ⅲ峰と続く。左の小さなピークが唐松岳だ。 6月中旬 |
|
|